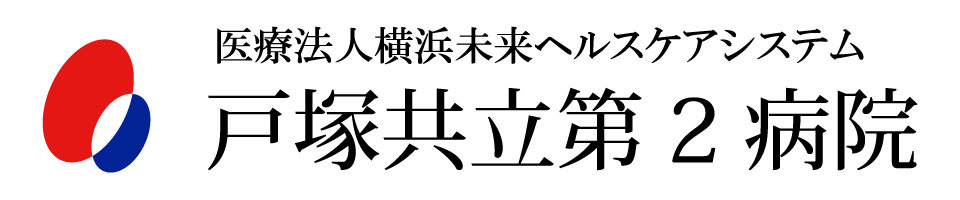令和6年度 戸塚共立第2病院 病院指標
病院指標
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞の患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
医療の質指標
- リスクレベルが「中」以上の手術を施行した患者の肺血栓塞栓症の予防対策の実施率
- 血液培養2セット実施率
- 広域スペクトル抗菌薬使用時の細菌培養実施率
- 転倒・転落発生率
- 転倒転落によるインシデント影響度分類レベル3b以上の発生率
- 手術開始前1時間以内の予防的抗菌薬投与率
- d2(真皮までの損傷)以上の褥瘡発生率
- 65歳以上の患者の入院早期の栄養アセスメント実施割合
- 身体的拘束の実施率
年齢階級別退院患者数
| 年齢区分 | 0歳~ | 10歳~ | 20歳~ | 30歳~ | 40歳~ |
|---|---|---|---|---|---|
| 患者数 | 53人 | 122人 | 109人 | 83人 | 168人 |
| 年齢区分 | 50歳~ | 60歳~ | 70歳~ | 80歳~ | 90歳~ |
| 患者数 | 264人 | 364人 | 629人 | 722人 | 277人 |
年齢階級別退院患者数は、2024年6月1日~2025年5月31日に退院された患者様の年齢を10歳刻みに集計した数となります。
当院では横浜市二次救急拠点病院であり、幅広い年齢層の患者様にご来院いただいております。
全体でみますと、70歳以上の入院患者様は1628名であり、59%を占めます。高齢化社会に対し、地域に密着した医療を担っております。
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
外科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数(自院) |
平均 在院日数(全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 | 29人 | 18.86日 | 20.78日 | 34.48% | 84.55歳 | |
| 060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上)ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 21人 | 3.71日 | 4.54日 | 4.76% | 72.67歳 | |
| 060160x101xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳未満)ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 21人 | 1.48日 | 2.73日 | 0.00% | 3.33歳 | |
| 0400800x99x0xx | 肺炎等(市中肺炎以外) | 13人 | 13.15日 | 18.16日 | 0.00% | 79.85歳 | |
| 060170xx02xx0x | 閉塞、壊疽のない腹腔のヘルニア | 13人 | 2.15日 | 6.85日 | 0.00% | 9.54歳 |
外科部門では、小児科領域と成人一般消化器外科領域の診療を行っております。
鼠径ヘルニアや腹壁ヘルニアに対する手術療法は乳児期以降超高齢者までを対象としており、幅広い年齢層に対応して治療を行っております。
鼠径ヘルニアとは、腸などが筋膜の間からはみ出して、足の付け根部分の皮膚の下に飛び出してしまう病気です。
小児の診療につきましては、小児外科専門医が担当しており、鼠径ヘルニアの全国平均と比較し下回っております。
整形外科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数(自院) |
平均 在院日数(全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160620xx01xxxx | 肘、膝の外傷(スポーツ障害等を含む。)関節鏡下靭帯断裂形成手術 十字靭帯 | 129人 | 11.62日 | 12.71日 | 0.00% | 31.00歳 | |
| 070343xx01x0xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。)腰部骨盤、不安定椎 脊椎固定術等 | 110人 | 19.74日 | 19.60日 | 4.55% | 72.82歳 | |
| 160800xx02xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術等 | 80人 | 27.98日 | 25.29日 | 51.25% | 82.11歳 | |
| 070343xx97x0xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。)腰部骨盤、不安定椎 その他の手術あり | 77人 | 5.00日 | 15.41日 | 0.00% | 70.57歳 | |
| 070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。)人工関節再置換術等 | 66人 | 22.83日 | 21.38日 | 3.03% | 76.00歳 |
整形外科では筋骨格系疾患や外傷を担当しております。特に『スポーツ医学センター』を設け、スポーツ選手の練習や試合、中高生の部活動等で負ったけがの治療に力を入れております。
膝関節の手術は主に靭帯再建術、半月板手術、症例によって高位脛骨骨切り術を行っております。
また、脊柱管狭窄症などに対する手術療法や、大腿骨骨折などの外傷にも数多く対応しており、手術後は早期に社会復帰に努めております。
大腿骨骨折は退院後に介護施設等を利用されるご高齢の方が多いため転院率が高くなっております。
心臓血管外科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 050180xx02xxxx | 静脈・リンパ管疾患 下肢静脈瘤血管内焼灼術 | 132人 | 1.61日 | 2.66日 | 0.00% | 67.69歳 | |
| 050080xx0101xx | 弁膜症(連合弁膜症を含む。)弁置換術 | 16人 | 23.13日 | 20.84日 | 6.25% | 77.88歳 | |
| 050130xx9900x0 | 心不全(他の病院・診療所の病棟からの転院以外) | 10人 | 10.90日 | 17.33日 | 10.00% | 88.00歳 | |
| 050163xx03x0xx | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術(腹部大動脈) | 10人 | 10.60日 | 10.18日 | 0.00% | 74.20歳 | |
| 0400800x99x0xx | 肺炎等(市中肺炎以外) | – | – | 18.16日 | – | – |
下肢静脈瘤については『横浜戸塚下肢静脈瘤センター』を開設し、専門的に治療をしております。
下肢静脈瘤とは、足の静脈が太くなって瘤(こぶ)状に浮き出て見えるようになった状態です。一旦発症すると治りにくく、加齢と共に症状が悪化するため早期の治療が大切です。
弁膜症とは、心臓にある4つの弁(大動脈弁、肺動脈弁、僧帽弁、三尖弁)のいずれかに異常が起こり、本来のポンプ機能を果たせなくなった病気のことです。
主な病態として、弁が開くのが悪くなる狭窄症と弁が閉じるのが不完全で血液が逆流してしまう閉鎖不全症があります。
軽症の場合は多くは無症状ですが、進行すると心臓が血液を充分に送れない状態(心不全)となり呼吸困難や全身のむくみなどが生じます。
※10症例未満の場合は、「-」で表示しております。
循環器科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患(PCI) | 91人 | 2.34日 | 4.18日 | 1.10% | 72.11歳 | |
| 050130xx9900x0 | 心不全(他の病院・診療所の病棟からの転院以外) | 89人 | 17.12日 | 17.33日 | 13.48% | 83.44歳 | |
| 050070xx03x0xx | 頻脈性不整脈(経皮的カテーテル心筋焼灼術) | 56人 | 3.64日 | 4.47日 | 0.00% | 66.29歳 | |
| 050050xx9920xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患(心臓カテーテル法による諸検査+血管内超音波検査等) | 47人 | 2.83日 | 3.27日 | 0.00% | 71.26歳 | |
| 050050xx9910xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患(CAG) | 38人 | 2.16日 | 3.07日 | 0.00% | 76.97歳 |
循環器科では主に心臓疾患の治療を担当し、狭心症については血管内カテーテル手術を行っております。
2つ目に多い症例は心不全です。心不全は心臓の動きが十分でない場合のことをいい、原因や自覚症状は人により様々です。退院後に介護施設等を利用されるご高齢の方が多いため、転院率が高くなっております。
当院では循環器内科と心臓血管外科が連携し、心臓や血管に病気のある患者様へ最適な医療を提供できるよう『循環器センター』を設立しております。
成人の循環器疾患は多種多様かつ進行性の疾患の為、病態に応じた治療が必要となります。循環器疾患は心臓や血管の病気が単一ではなく複合して発症していることも多々あります。
患者様一人一人に合った治療方針を決定し、最良の医療を提供してまいります。
内科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10007xxxxxx1xx | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)インスリン製剤 | 30人 | 11.40日 | 13.77日 | 10.00% | 69.83歳 | |
| 040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 | 28人 | 22.79日 | 20.78日 | 17.86% | 85.54歳 | |
| 110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 | 19人 | 11.63日 | 13.66日 | 5.26% | 77.32歳 | |
| 0400800x99x0xx | 肺炎等(市中肺炎以外) | 17人 | 12.88日 | 18.16日 | 5.88% | 74.06歳 | |
| 0400802299×001 | 肺炎等(市中肺炎かつ15歳以上65歳未満)A-DROPスコア1 | 10人 | 6.90日 | 9.71日 | 10.00% | 39.10歳 |
内科では呼吸器疾患を中心に幅広く対応しております。食物や唾液などの誤嚥によって引き起こされる誤嚥性肺炎は80歳を超える高齢者の方に多い傾向にあります。そのため、退院支援部門として医療ソーシャルワーカーと専従の退院支援看護師を配置し、各患者様のニーズに合わせた退院支援を行っております。また、戸塚区内で近隣の医療機関や介護老人保健施設等と密に連携しており、より多くの患者様の受入を積極的に行っております。
当院で最も症例数の多い糖尿病は、一度発症すると完全には治癒することのない病気で、インスリンの働きが弱くなり血糖が高い状態が続いてしまいます。長年の食生活等が背景にあり短期間で変えていくことは難しいと言われています。当院では、糖尿病専門医による食事、運動、薬物療法などの管理方法を入院して学んでいただく教育入院の患者様を積極的に受け入れております。
乳腺外科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数(自院) |
平均 在院日数(全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 090010xx010xxx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房切除術等 | 44人 | 6.91日 | 9.77日 | 0.00% | 68.91歳 | |
| 090010xx02xxxx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術等 | 42人 | 4.33日 | 5.50日 | 0.00% | 63.40歳 | |
| 090020xx97xxxx | 乳房の良性腫瘍 その他手術あり | 15人 | 2.33日 | 3.94日 | 0.00% | 47.87歳 | |
| 090010xx99x0xx | 乳房の悪性腫瘍 手術なし | – | – | 9.75日 | – | – | |
| 090010xx99x6xx | 乳房の悪性腫瘍 トラスツズマブ | – | – | 3.65日 | – | – |
乳腺外科は、乳房の悪性腫瘍・良性腫瘍の治療を行っております。関連クリニックで診療・検診を行い、手術適応となった患者様の手術を当院で実施しております。
患者様の病態やニーズに合わせて複数の選択肢の中から、最も適した治療法を提案しております。乳癌の治療には抗がん剤治療もあり、様々な副作用を伴うこともあります。副作用をできるだけ軽減するための薬も積極的に使用し、苦痛の少ない治療を心がけております。
※10症例未満の場合は、「-」で表示しております。
耳鼻咽喉科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 | 27人 | 5.11日 | 5.63日 | 0.00% | 41.52歳 | |
| 030400xx99xxxx | 前庭機能障害 | 17人 | 4.76日 | 4.67日 | 0.00% | 68.47歳 | |
| 030240xx01xx0x | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 扁桃周囲膿瘍切開術等 | – | – | 7.65日 | – | – | |
| 030270xxxxxxxx | 上気道炎 | – | – | 4.71日 | – | – | |
| 030380xxxxxxxx | 鼻出血 | – | – | 5.19日 | – | – |
耳鼻咽喉科では、めまい、耳鳴り、難聴をきたす等の疾患に対して適切な治療を行っております。
難聴の患者様に対しては、補聴器外来を行っております。
扁桃周囲膿瘍や扁桃炎は、感染により扁桃の後部に膿が貯留する疾患です。
急性扁桃炎が進行し、扁桃周囲膿瘍になってしまうと、口から膿瘍を切開して膿を出す手術を行うため、数日間の入院が必要となります。
※10症例未満の場合は、「-」で表示しております。
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
| 初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
| 胃癌 | – | – | – | – | – | – | 1 | 8 |
| 大腸癌 | – | – | – | – | – | – | 2 | 8 |
| 乳癌 | 30 | 34 | 11 | – | – | – | 1 | 8 |
| 肺癌 | – | – | – | – | – | – | 1 | 8 |
| 肝癌 | – | – | – | – | – | – | 2 | 8 |
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
癌の症例に関してはカンファレンスを行い、癌の進行状況に応じ、患者様の状態に合わせた幅広い治療を実施しております。
※10症例未満の場合は、「-」で表示しております。
成人市中肺炎の重症度別患者数等
| 患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
|---|---|---|---|
| 軽症 | – | – | – |
| 中等症 | 37人 | 10.19日 | 65.14歳 |
| 重症 | – | – | – |
| 超重症 | – | – | – |
| 不明 | – | – | – |
肺炎は日本人の死因の第5位です。感染症の市中肺炎は高齢化するほど重症度が上がる傾向がみられます。適切な抗生剤の使用、更に長期入院には筋力・体力低下を防ぐため、早期のリハビリテーションを導入した加療を行っております。
※10症例未満の場合は、「-」で表示しております。
脳梗塞の患者数等
| 発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
|---|---|---|---|---|
| 3日以内 | – | – | – | – |
| その他 | – | – | – | – |
当院はCTやMRIを有し、脳梗塞と診断され専門的な治療を必要とする場合は、迅速に専門医のいる病院へ転院の手続きをいたします。
※10症例未満の場合は、「-」で表示しております。
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
外科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K6335 | 鼠経ヘルニア手術 | 48人 | 0.67日 | 0.75日 | 2.08% | 33.58歳 | |
| K6333 | 臍ヘルニア手術 | 11人 | 0.91日 | 0.00日 | 0.00% | 1.09歳 | |
| K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2㎝未満) | – | – | – | – | – | |
| K8282 | 包茎手術(環状切除術) | – | – | – | – | – | |
| K836 | 停留精巣固定術 | – | – | – | – | – |
最も手術症例が多いのは、鼠経ヘルニア手術です。次に多い症例は、臍ヘルニア手術です。
※10症例未満の場合は、「-」で表示しております。
整形外科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K1422 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(後方又は後側方固定) | 156人 | 3.58日 | 18.02日 | 8.97% | 73.85歳 | |
| K0821 | 人工関節置換術(膝) | 127人 | 1.56日 | 18.40日 | 5.51% | 72.52歳 | |
| K128 | 脊椎内異物(挿入物)除去術 | 88人 | 1.10日 | 3.01日 | 0.00% | 70.97歳 | |
| K079-21 | 関節鏡下靭帯断裂形成手術(十字靭帯) | 79人 | 1.00日 | 9.57日 | 0.00% | 27.67歳 | |
| K0461 | 骨折観血的手術(大腿) | 51人 | 3.69日 | 18.12日 | 41.18% | 81.55歳 |
当院では、脊椎疾患や人工関節(股関節および膝関節)を中心とした「人工関節センタ-」とスポーツにおける外傷に対して治療を行う「スポーツ医学センター」に力を入れております。
脊椎疾患では、加齢や変形した椎間板と、背骨や椎間関節から突出した骨などにより、神経が圧迫される腰部脊柱管狭窄症に対する脊椎固定術や抜釘術が最も多くなっております。
人工関節置換術とは、軟骨が損傷し痛んだ関節の表面を金属やセラミックス、ポリエチレン等のインプラントに置換し痛みを取り除く手術です。関節の機能再建を目的として行います。
当院では両側37件、片側90件と手術実績が多く、手術翌日から歩行訓練を開始し、歩行能力の改善を図っております。
スポーツ医学センターではスポーツで負ったけがを中心に、関節鏡を用いた十字靱帯の断裂形成手術が第4位と多く実施されています。こちらの方々は比較的若い方が多く、平均年齢も20歳台となっております。早期に手術を行い、リハビリを実施し、患者様が少しでも早く日常生活に復帰できるよう努めています。
心臓血管外科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K617-6 | 下肢静脈瘤血管内塞栓術 | 82人 | 0.00日 | 0.45日 | 0.00% | 75.29歳 | |
| K617-4 | 下肢静脈瘤血管内焼灼術 | 38人 | 0.00日 | 0.84日 | 0.00% | 52.80歳 | |
| K5552 | 弁置換術(2弁のもの) | 10人 | 2.10日 | 17.10日 | 0.00% | 76.40歳 | |
| K6171 | 下肢静脈瘤手術(抜去切除術) | 10人 | 0.00日 | 1.00日 | 0.00% | 60.80歳 | |
| K5612ロ | ステントグラフト内挿術(腹部大動脈) | – | – | – | – | – |
「横浜戸塚下肢静脈瘤センター」を開設し、高周波機器を用いた血管内焼灼術による治療を行っております。これは皮膚を切開せずカテーテルを静脈に刺入し、高周波照射することで静脈を焼灼し、中心から閉塞させる方法です。さらに、グルー(医療用接着剤)を静脈内に注入し閉塞させる血管内塞栓術を実施しております。
※10症例未満の場合は、「-」で表示しております。
循環器科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) | 83人 | 0.86日 | 1.69日 | 0.00% | 72.77歳 | |
| K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | 46人 | 0.74日 | 8.11日 | 2.17% | 78.59歳 | |
| K5951 | 経皮的カテーテル心筋焼灼術(心房中隔穿刺、心外膜アプローチ) | 44人 | 1.00日 | 2.16日 | 0.00% | 68.41歳 | |
| K5972 | ペースメーカー移植術(経静脈電極) | 13人 | 1.69日 | 7.69日 | 0.00% | 79.85歳 | |
| K5952 | 経皮的カテーテル心筋焼灼術(その他) | 12人 | 0.25日 | 1.17日 | 0.00% | 59.17歳 |
PCIと呼ばれる経皮的冠動脈形成術を実施しております。カテーテルという細長い管を太ももの付け根、手首あるいは肘の動脈から冠動脈まで挿入し、このカテーテルを通じて冠動脈の狭窄や閉塞に対してステント(金属製の網目状パイプ)を挿入し拡張する治療です。同様にカテーテルを用いた手術となる血管内拡張術・血栓除去術を行っております。また、ペースメーカー移植術(経静脈電極)を実施しております。
乳腺外科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K4762 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わない)) | 42人 | 0.98日 | 2.36日 | 0.00% | 63.40歳 | |
| K4763 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房切除術(腋窩部郭清を伴わない)) | 25人 | 1.08日 | 5.04日 | 0.00% | 71.20歳 | |
| K4765 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房切除術・腋窩部郭清あり・胸筋切除を併施しない) | 13人 | 1.54日 | 5.15日 | 0.00% | 66.85歳 | |
| K4741 | 乳腺腫瘍摘出術(長径5㎝未満) | – | – | – | – | – | |
| K4742 | 乳腺腫瘍摘出術(長径5㎝以上) | – | – | – | – | – |
乳癌に対する手術の原則は、癌を全て取り除くことにあります。その中でも、比較的元通りに近い形態で乳房が残せると考えられる場合には、乳房温存手術を行うこともあります。患者様一人ひとりの病態やニーズに合わせ、複数の選択肢の中から、最も適した治療法を提案することが大切だと考えています。場合によっては無理に温存手術をするよりも、組織拡張器を用いた同時再建術の方が望ましい事もありますし、薬物療法を先に行い癌を小さくしてから温存手術をする方法なども提案しております。
※10症例未満の場合は、「-」で表示しております。
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
| DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
|---|---|---|---|---|
| 130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | – | – |
| 異なる | – | – | ||
| 180010 | 敗血症 | 同一 | – | – |
| 異なる | – | – | ||
| 180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | – | – |
| 異なる | – | – | ||
| 180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 14人 | 0.50% |
| 異なる | – | – |
播種性血管内凝固症候群(DIC)は敗血症や重篤な症状に陥りやすく、迅速な加療が求められます。当院ではそういった状況に即座に対処すべき経験のある医師が病状に応じた治療を行っております。
手術・処置等の合併症においても同様に治療を行っております。全く発症させなくすることは困難ですが、少しでも改善できるよう努めております。
※10症例未満の場合は、「-」で表示しております。
リスクレベルが「中」以上の手術を施行した患者の肺血栓塞栓症の予防対策の実施率
| 肺血栓塞栓症発症のリスクレベルが「中」以上の手術を施行した退院患者数(分母) | 836人 |
| 分母のうち、肺血栓塞栓症の 予防対策が実施された患者数(分子) |
677人 |
| リスクレベルが「中」以上の手術を施行した患者の肺血栓塞栓症の予防対策の実施率 | 79.78% |
肺血栓塞栓症とは、肺動脈に血液の塊である血栓が詰まる病気です。多くの場合は、長期臥床で長い間、一定の姿勢を取ることにより下肢の静脈に形成された血栓が、肺まで運ばれてくることから肺血栓塞栓症を発症します。
予防としては脱水を起こすと血栓形成のリスクが高まるため長時間座ったり寝たりする必要がある場合には適度に水分摂取を心がけることが大切です。また、屈伸運動や歩いたりすることも効果的です。
当院では、血栓形成を予防するために医師の指示のもと弾性ストッキングを使用し早期のリハビリの介入を行っています。
血液培養2セット実施率
| 血液培養オーダー日数(分母) | 354日 |
| 血液培養オーダーが1日に 2件以上ある日数(分子) |
244日 |
| 血液培養2セット実施率 | 68.93% |
感染源からの分泌物(痰や尿など)を調べ、病原菌を特定する検査を「培養検査」といい、血液内の病原菌の有無を調べることを「血液培養検査」といいます。この血液培養検査では、検査の精度を向上させるために1回2セット以上を採取することがガイドラインにて推奨されており、実施率をモニタリングすることは感染症治療を行う上で非常に重要です。当院では、血液培養検査をオーダー発行するときは自動的に2セットで発行するなど実施率向上に向け活動を行っておりますが、2024年度は血液培養ボトルの流通悪化で1セットしか実施できない時期もあったため血液培養2セット実施率が下がっております。
広域スペクトル抗菌薬使用時の細菌培養実施率
| 広域スペクトルの抗菌薬が 処方された退院患者数(分母) |
66人 |
| 分母のうち、入院日以降抗菌薬処方日 までの間に細菌培養同定検査が 実施された患者数(分子) |
47人 |
| 広域スペクトル抗菌薬使用時の 細菌培養実施率 |
71.21% |
感染症診療において原因となる微生物を特定し、それに対する治療を行うことは大変重要なことです。
特に経験的治療として幅広い範囲の細菌を標的として抗菌薬を使用する場合は、投与開始前に培養検査が必要とされています。
当院では、感染症を疑った場合、抗菌薬の種類に関わらず事前に各種培養検査を行っております。原因菌が判明後は、必要に応じて狭域の抗菌薬へ変更を行うことで確実な効果が得られるとともに耐性菌の出現をできるだけ抑えるよう尽力しております。
転倒・転落発生率
| 退院患者の在院日数の総和 もしくは入院患者延べ数(分母) |
31088人 |
| 退院患者に発生した転倒・転落件数(分子) | 91件 |
| 転倒・転落発生率 | 2.93‰ |
転倒・転落による傷害発生事例の件数は少なくても、それより多く発生している傷害に至らなかった事例も併せて報告し、発生件数を追跡するとともに、それらの事例を分析することで、より転倒転落発生要因を特定しやすくなります。
予防策を実施し、転倒・転落発生リスクを低減していく取り組みが転倒による傷害予防につながります。
当院では、転倒・転落予防として、アセスメントシートを作成し患者評価をしております。また、もし転倒・転落をしてしまった場合のフローチャートを作成し迅速に対応しております。
転倒転落によるインシデント影響度分類レベル3b以上の発生率
| 退院患者の在院日数の総和 もしくは入院患者延べ数(分母) |
– |
| 退院患者に発生したインシデント 影響度分類レベル3b以上の 転倒・転落の発生件数(分子) |
– |
| 転倒転落によるインシデント影響度 分類レベル3b以上の発生率 |
– |
転倒・転落による傷害発生事例の件数は少なくても、それより多く発生している傷害に至らなかった事例も併せて報告し、発生件数を追跡するとともに、それらの事例を分析することで、より転倒転落発生要因を特定しやすくなります。
予防策を実施し、転倒・転落発生リスクを低減していく取り組みが転倒による傷害予防につながります。
当院では、転倒・転落予防として、アセスメントシートを作成し患者評価をしております。また、もし転倒・転落をしてしまった場合のフローチャートを作成し迅速に対応しております。
手術開始前1時間以内の予防的抗菌薬投与率
| 全身麻酔手術で、 予防的抗菌薬投与が実施された 手術件数(分母) |
1206件 |
| 分母のうち、手術開始前 1時間以内に予防的抗菌薬が 投与開始された手術件数(分子) |
1206件 |
| 手術開始前1時間以内の 予防的抗菌薬投与率 |
100.00% |
当院では予防として全患者様に予防的抗菌薬の投与を行っております。
d2(真皮までの損傷)以上の褥瘡発生率
| 退院患者の在院日数の総和もしくは 除外条件に該当する患者を除いた 入院患者延べ数(分母) |
– |
| 褥瘡(d2(真皮までの損傷)以上 の褥瘡)の発生患者数(分子) |
– |
| d2(真皮までの損傷)以上の 褥瘡発生率 |
– |
当院では院内での褥瘡発生の予防として、皮膚の観察や定期的な体位変換、除圧等さまざまな形で対策をしております。
65歳以上の患者の入院早期の栄養アセスメント実施割合
| 65歳以上の退院患者数(分母) | 1745人 |
| 分母のうち、入院後48時間以内に 栄養アセスメントが実施された患者数(分子) |
1690人 |
| 65歳以上の患者の入院早期の 栄養アセスメント実施割合 |
96.85% |
当院では管理栄養士が6人在籍しており、患者様の体重変化、血液データ、食事歴などから総合的に栄養状態を判定し、栄養の改善に努めております。
栄養管理は全ての医療の基盤であり、疾病の治癒や予後に大きく影響します。特に高齢者の栄養管理は入院中の治療やリハビリ訓練だけでなく、退院後の生活にも影響します。当院では通常、入院初日に全ての入院患者様に栄養スクリーニングを実施し、3日以内に多職種による栄養管理計画書を作成します。早期栄養介入を多職種で行うことで、治療の促進に努めております。
身体的拘束の実施率
| 退院患者の在院日数の総和(分母) | 31088人 |
| 分母のうち、身体的拘束日数の総和(分子) | 3007人 |
| 身体的拘束の実施率 | 9.67% |
当院では拘束を無くしていくため、まず現状を見直し、身体拘束の最小化・適正化を目指しています。危険を防ぐために拘束が必要と考えられた際には、本人・家族双方に説明の上、同意書を得て拘束させていただく場合があります。拘束した場合でも、早期解除を目指し、毎日のカンファレンスと週1回のラウンドの施行をしています。